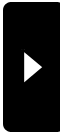2014年10月28日
2014年10月28日
2014年10月28日
2014年10月28日
2014年03月24日
【2月・3月のイベント販売の様子】
2月1日・2日 サンライフ藤枝祭り




2月27日 ふじのくに商談会


3月1日 お日まち処・白子100円笑店街



3月22日 志太ぐんがまつり



3月23日 青北まつり


みなさん、ありがとうございました!!




2月27日 ふじのくに商談会


3月1日 お日まち処・白子100円笑店街



3月22日 志太ぐんがまつり



3月23日 青北まつり


みなさん、ありがとうございました!!
Posted by かぜ at
08:41
│Comments(0)
2014年01月15日
遅くなりました…が明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。 ~風一同より~

去年のクリスマス会の写真(まだありましたのでアップします)
ビンゴ大会とカラオケ大会




1月11日 白子100円笑店街 出店模様


~番外編~
年末、有志と行く鎌倉・伊東旅行








去年のクリスマス会の写真(まだありましたのでアップします)
ビンゴ大会とカラオケ大会





1月11日 白子100円笑店街 出店模様


~番外編~
年末、有志と行く鎌倉・伊東旅行







Posted by かぜ at
11:34
│Comments(0)
2013年12月24日
2013年11月25日
2013年11月19日
平成25年11月 7日 ネットワーク会議での発表 (安本智己さん)
智己に今日のスピーチを頼んだら、熱が出て2日間食事が出来なくなってしまいました。
智己の話を私(岸理事長)が書いて読むことにしたら、熱も下がり食事もとれるようになったので、私が読ませて頂きます。
僕の時代はまだ藤枝養護学校がなかったので静岡北養護学校の高等部を卒業しました。そして藤枝の木工所に入社しました。8年間勤めましたが工場がつぶれてしまいました。すぐに他の木工所に入社しましたが、いじめられて辛い思いをしている事に、お母さんが気付いてその木工所をやめました。15年ぐらい前のことです。
まだその頃は障害者施設が障害別になっていて、知的障害の作業所にお願いしましたが、そこも断られてしまいました。2年間家にいて、日曜日しか外に出る事が出来なくてとても辛かったです。
お母さんの友達が「岸さんが行く所の無い人達と農業や養蜂をやっているからそこへいってみるといいよ。」と、教えてくれて、そこに通うようにしました。
ここが今のNPO法人「風」になりました。それからベーカリーカフェ「風」が出来て、そこで作業するようになりました。ベーカリーカフェには最初からいて、今はパンの生地作りや、販売やパンの仕分けなど、いろんな事をやっています。
グループホーム「緑の風」に入所して、今は年金と工賃で暮らしていけるようになりました。
一番辛かったのは仕事に行く所が無いことでした。これからも頑張って元気に仕事をしていきます。宜しくお願いします。
安本智己
すみませんが補足させて頂きます。
今朝、智己のお母さんにこの文を読み聞かせたところ、ひとつ違う所があるとの事でした。それは2回目の木工所の事です。この話を聞いて気分が悪くなる方がいましたらすみません。
2年の契約で入社しましたが、その契約期間が経ちお母さんが社長の所に伺ったら「2年間、無視して、いじめても会社を辞めずにそれどころか一番早く出社してくる。」と、思いもよらぬ言葉を聞かされ、智己に「もう一般の会社にいかなくていい、授産所が決まるまで家にいるように」と言い、つれて帰ったと、目を潤ませて言っていました。
その会社はつぶれ、社長は両足をなくしたそうです。
余分な話をしてすみませんでした。以上です。
上記の文面は岸理事長補足文

智己の話を私(岸理事長)が書いて読むことにしたら、熱も下がり食事もとれるようになったので、私が読ませて頂きます。
僕の時代はまだ藤枝養護学校がなかったので静岡北養護学校の高等部を卒業しました。そして藤枝の木工所に入社しました。8年間勤めましたが工場がつぶれてしまいました。すぐに他の木工所に入社しましたが、いじめられて辛い思いをしている事に、お母さんが気付いてその木工所をやめました。15年ぐらい前のことです。
まだその頃は障害者施設が障害別になっていて、知的障害の作業所にお願いしましたが、そこも断られてしまいました。2年間家にいて、日曜日しか外に出る事が出来なくてとても辛かったです。
お母さんの友達が「岸さんが行く所の無い人達と農業や養蜂をやっているからそこへいってみるといいよ。」と、教えてくれて、そこに通うようにしました。
ここが今のNPO法人「風」になりました。それからベーカリーカフェ「風」が出来て、そこで作業するようになりました。ベーカリーカフェには最初からいて、今はパンの生地作りや、販売やパンの仕分けなど、いろんな事をやっています。
グループホーム「緑の風」に入所して、今は年金と工賃で暮らしていけるようになりました。
一番辛かったのは仕事に行く所が無いことでした。これからも頑張って元気に仕事をしていきます。宜しくお願いします。
安本智己
すみませんが補足させて頂きます。
今朝、智己のお母さんにこの文を読み聞かせたところ、ひとつ違う所があるとの事でした。それは2回目の木工所の事です。この話を聞いて気分が悪くなる方がいましたらすみません。
2年の契約で入社しましたが、その契約期間が経ちお母さんが社長の所に伺ったら「2年間、無視して、いじめても会社を辞めずにそれどころか一番早く出社してくる。」と、思いもよらぬ言葉を聞かされ、智己に「もう一般の会社にいかなくていい、授産所が決まるまで家にいるように」と言い、つれて帰ったと、目を潤ませて言っていました。
その会社はつぶれ、社長は両足をなくしたそうです。
余分な話をしてすみませんでした。以上です。
上記の文面は岸理事長補足文

Posted by かぜ at
12:14
│Comments(1)
2013年11月07日
あたたかいご声援ありがとうございました!


お手紙ありがとうございます。みんなの励みになります。
とてもおいしそうに書いていただきありがとうございます。
Posted by かぜ at
11:23
│Comments(0)
2013年11月06日
2013年11月02日
きすみれフェスタ・障害者フェア・わかふじまつり 【その2】



10月・11月とイベント大忙し!!!
どこかで見かけていただけたら応援してください。

Posted by かぜ at
05:10
│Comments(0)
2013年11月02日
2013年11月02日
2013年09月13日
流しそうめん・スイカ割り・カラオケ大会
風の仲間の夏祭りを行いました。
流しそうめんやスイカ割りカラオケ大会をやりました。
成島雅人様から寄付を頂戴し、カラオケセットと購入の一部とさせて頂きました。歌が好きな利用者さんが多いのでとても楽しく使わせていただいております。ありがとうございました。








流しそうめんやスイカ割りカラオケ大会をやりました。
成島雅人様から寄付を頂戴し、カラオケセットと購入の一部とさせて頂きました。歌が好きな利用者さんが多いのでとても楽しく使わせていただいております。ありがとうございました。









Posted by かぜ at
11:32
│Comments(0)
2013年09月13日
大石くんの思い出
在りし日の大石隆仁君が着用していた思い出の洋服類をご家族様からいただき、仲間で選びあってそれぞれ頂きました。大切に着させていただきます。 ありがとうございました。 合掌












Posted by かぜ at
11:13
│Comments(0)
2013年09月12日
【英文】 Sakuyahime Project Page2
4).The Decision
I finally reached the decision that there was no way except to make a place for him by myself.
I rented 198 sq meter of land and began to grow vegetables with him. I had the confidence that working outside in nature must be the best way to cure his mental condition. Another reason was that I realized there were a lot of people who didn’t have a place to go, when they had both social and mental handicaps. There were no places to accept them. They had to stay home as recluses. They didn’t like social contact. Gradually mothers who had such kinds of problems began to gather around me, and we tried to share how to solve the same kind of problems. The reclusive people also began to gather at my home, spending the days with Ryo.
I wanted to give them the joy of working on the farm. We grew chemical free vegetables, egg plants, cucumbers, and tomatoes. I paid them per hour, and even a small amount gave them the pleasure of getting wages by labor. All I wanted was to let the know the joy of work.
We tried beekeeping, made boxes by ourselves and got honey.
But there were problems. Ryo sometimes began to go on rampages, so agricultural machines and scythes were dangerous. In the farm, one idea suddenly came to my mind; “growing wheat and baking breads “ But wheat for the bread is usually cultivate in a cold climate. Fujieda city’s weather is very mild, and isn’t suited for growing wheat.
5) Nishino Hikari
I got the information of an academic meeting about domestic wheat to be held in Tokyo. It was 2002. I took part in that meeting. There was a researcher of Nishino Hikari, a breed of wheat for baking bread, which grows in areas with mild weather. Kyushu and Okinawa agricultural institutions were researching this breed. Kyushu and Okinawa are located in the southern part of Japan, It was still difficult to get these seeds. I begged researchers to give me them telling them why I wanted to grow this wheat, and bake bread with handicapped people in Shizuoka Prefecture. They granted my request and gave the 20 kilograms of seeds.
Growing Nishino Hikari was extremely difficult. I can’t tell how difficult it was in the words.
None of us had experience growing Nishino Hikari, Above all, the rainy season was prolonged that year. We did not use insecticides, so the wheat got damaged by insects. I didn’t even have a reaping machine, so I reaped by scythe alone 198 meter sq farm in the rain.
Another problem was there was no place to store the wheat. I visited farmers in my neighborhood, and asked to lend the barns to store them.
6))Opening of “Bakery caffe Kaze”
At last, I reached the time of opening the “Bakery Caffe Kaze” in November 2002. Kaze literally means wind in Japanese. I used the compensation of the accident and my savings for the construction of Kaze. I didn’t know about the compensation for a long time. One day the insurance company’s man visited me and asked “Are you expecting something for the compensation?” I could not understand what he meant. At that time 8 years had passed since Ryo was involved in the accident. Never had I thought about the compensation, I devoted all my energy to finding Ryo’s hospital, farming and his place to belong.
Before I opened Bakery Caffe Kaze, I established “Kaze” an NPO. The aim of the construction of “Bakery Caffe Kaze” was to make a working place for reclusive people, like Ryo, who have no place to belong in the society. I publicly informed reclusive people about working here. 10 handicapped people and about 5 volunteers came to work. Our effort bore fruit. We did everything by ourselves,
We baked bread using flour made from Nishino Hikari which we grew. We baked, sold,and served the customers .
Bakery coffe Kaze is locatied in a local area, most residents are farmers, and connection of the neighborhood is very strong. At first, people had prejudice. I visited each and every family and tried to make them understand our aim of Bakery Caffe Kaze. They gradually understood and accepted us.
7) Facing the limits after 10 years and the necessity of public help
Since Bakery Caffe Kaze opened, everything was managed without public support.
Thanks to the help of local people and customers, we could run the Bakery Caffe Kaze.
We always tried to bake the best bread with the best quality materials. We did not want to use the fact that bread is baked by the handicapped people as an excuse.
We could run Bakery Caffe without public support. We worked hard with only two hours sleep at night, and got the minimum wage for running the bakery Kaffe. We did everything we could do.
Finally, we had to ask for public support at the local city office. We had reached the limit running Bakery Caffe. I visited city office many times to ask for the public support for the people who don’t have a place to belong.
However, there was a high wall between city office and us, the administrative law was too strict for us to overcome. One city officer told me that you are just a Bakery.
He also advised me that there are still a lot of vacancies in the places for handicapped people. But actually there are a lot of handicapped people who were not able to belong to any of those places. I told him they needed to choose a place to suit for them. Actually there are a lot of people in the shade of public support. That is the reality. I strongly insisted on that point. Gradually city office admitted our daily effort in Bakery Caffe Kaze, how handicapped people were making great efforts to run Bakery Caffe Kaze. At last We could get the city support in 2011. At last I could hire staffs.
8)Fujieda City Regional life Support Center
This place is the workshop for the people who can’t work in Bakery Caffe Kaze.
I reformed my own house and handicapped people spend the days doing creative activities and light work. 30 people are registered. About 10 people use it every day.
Some of them just come and sleep all day and chat with the others at lunch
time. But it was first step for them to associate with other people.
9)Group Home Green Wind
I constructed the Group Home Green Wind. That was my long dream.
There are eights private rooms, and residents are under care of the staff.
Staff help clean rooms and cook dinner every day. I used my own money for the construction. But this time I already got the city to support us, and city office supported this construction.
10)Ryo
Ryo does not act violently any more. He has own place and friends. Gradually he regained his memory. He never even slightly loses his temper. When I mentioned how he acted violently, he laughed and said he was still a child at that time. He likes English and studies English Grammar by PC by himself. He writes short stories in English. He also likes karaoke and goes to karaoke shop alone to sing songs .He spends long hours singing songs with his companions.
These past 20 years have been very long. First I was involved in this work for Ryo. I had to do something for Ryo. But during the process, my origin to do this work changed to anger at the administration. I am still fighting against prejudice and negligence of handicapped people. I am fighting with the administration on behalf of handicapped people. My friends often wonder how I can act like this without crying.
Actually I never cried even when I was told by doctors that there was a 99.9% chance Ryo could not survive. I really never gave up his surviving. The sentence of 99.9% impossibility of surviving gave me the energy to make him survive. I did not accept this sentence seriously, I only thought he can survive, and I did everything what I could.
I believe my next dream will come true, too. That is the progress convincing the administration dealing with handicapped people to make them aware what being handicapped really is, and what they have to do for handicapped as administration without prejudice.
Above I have written my struggle for establishing Bakery Caffe Wind, Group Home Green Wind, and Regional life support Center NPO. I really want to know about the welfare in the world for cases like Ryo’s.; how administration is facing them in the world. What kind of organizations and institutions exist.
I would appreciate it if someone in the world who is involved in this field could send me some information. Also I want to let the people know my struggle as it is written above.
誰もがいつ障害者になるか誰もが考えてほしい事です。誰もが希望を持って生きていける社会作りに関心を持っていただきたく、いろんな国の人達の意見が聞きたいと英文にしました。
NPO法人 風 理事長 岸 俊子
I finally reached the decision that there was no way except to make a place for him by myself.
I rented 198 sq meter of land and began to grow vegetables with him. I had the confidence that working outside in nature must be the best way to cure his mental condition. Another reason was that I realized there were a lot of people who didn’t have a place to go, when they had both social and mental handicaps. There were no places to accept them. They had to stay home as recluses. They didn’t like social contact. Gradually mothers who had such kinds of problems began to gather around me, and we tried to share how to solve the same kind of problems. The reclusive people also began to gather at my home, spending the days with Ryo.
I wanted to give them the joy of working on the farm. We grew chemical free vegetables, egg plants, cucumbers, and tomatoes. I paid them per hour, and even a small amount gave them the pleasure of getting wages by labor. All I wanted was to let the know the joy of work.
We tried beekeeping, made boxes by ourselves and got honey.
But there were problems. Ryo sometimes began to go on rampages, so agricultural machines and scythes were dangerous. In the farm, one idea suddenly came to my mind; “growing wheat and baking breads “ But wheat for the bread is usually cultivate in a cold climate. Fujieda city’s weather is very mild, and isn’t suited for growing wheat.
5) Nishino Hikari
I got the information of an academic meeting about domestic wheat to be held in Tokyo. It was 2002. I took part in that meeting. There was a researcher of Nishino Hikari, a breed of wheat for baking bread, which grows in areas with mild weather. Kyushu and Okinawa agricultural institutions were researching this breed. Kyushu and Okinawa are located in the southern part of Japan, It was still difficult to get these seeds. I begged researchers to give me them telling them why I wanted to grow this wheat, and bake bread with handicapped people in Shizuoka Prefecture. They granted my request and gave the 20 kilograms of seeds.
Growing Nishino Hikari was extremely difficult. I can’t tell how difficult it was in the words.
None of us had experience growing Nishino Hikari, Above all, the rainy season was prolonged that year. We did not use insecticides, so the wheat got damaged by insects. I didn’t even have a reaping machine, so I reaped by scythe alone 198 meter sq farm in the rain.
Another problem was there was no place to store the wheat. I visited farmers in my neighborhood, and asked to lend the barns to store them.
6))Opening of “Bakery caffe Kaze”
At last, I reached the time of opening the “Bakery Caffe Kaze” in November 2002. Kaze literally means wind in Japanese. I used the compensation of the accident and my savings for the construction of Kaze. I didn’t know about the compensation for a long time. One day the insurance company’s man visited me and asked “Are you expecting something for the compensation?” I could not understand what he meant. At that time 8 years had passed since Ryo was involved in the accident. Never had I thought about the compensation, I devoted all my energy to finding Ryo’s hospital, farming and his place to belong.
Before I opened Bakery Caffe Kaze, I established “Kaze” an NPO. The aim of the construction of “Bakery Caffe Kaze” was to make a working place for reclusive people, like Ryo, who have no place to belong in the society. I publicly informed reclusive people about working here. 10 handicapped people and about 5 volunteers came to work. Our effort bore fruit. We did everything by ourselves,
We baked bread using flour made from Nishino Hikari which we grew. We baked, sold,and served the customers .
Bakery coffe Kaze is locatied in a local area, most residents are farmers, and connection of the neighborhood is very strong. At first, people had prejudice. I visited each and every family and tried to make them understand our aim of Bakery Caffe Kaze. They gradually understood and accepted us.
7) Facing the limits after 10 years and the necessity of public help
Since Bakery Caffe Kaze opened, everything was managed without public support.
Thanks to the help of local people and customers, we could run the Bakery Caffe Kaze.
We always tried to bake the best bread with the best quality materials. We did not want to use the fact that bread is baked by the handicapped people as an excuse.
We could run Bakery Caffe without public support. We worked hard with only two hours sleep at night, and got the minimum wage for running the bakery Kaffe. We did everything we could do.
Finally, we had to ask for public support at the local city office. We had reached the limit running Bakery Caffe. I visited city office many times to ask for the public support for the people who don’t have a place to belong.
However, there was a high wall between city office and us, the administrative law was too strict for us to overcome. One city officer told me that you are just a Bakery.
He also advised me that there are still a lot of vacancies in the places for handicapped people. But actually there are a lot of handicapped people who were not able to belong to any of those places. I told him they needed to choose a place to suit for them. Actually there are a lot of people in the shade of public support. That is the reality. I strongly insisted on that point. Gradually city office admitted our daily effort in Bakery Caffe Kaze, how handicapped people were making great efforts to run Bakery Caffe Kaze. At last We could get the city support in 2011. At last I could hire staffs.
8)Fujieda City Regional life Support Center
This place is the workshop for the people who can’t work in Bakery Caffe Kaze.
I reformed my own house and handicapped people spend the days doing creative activities and light work. 30 people are registered. About 10 people use it every day.
Some of them just come and sleep all day and chat with the others at lunch
time. But it was first step for them to associate with other people.
9)Group Home Green Wind
I constructed the Group Home Green Wind. That was my long dream.
There are eights private rooms, and residents are under care of the staff.
Staff help clean rooms and cook dinner every day. I used my own money for the construction. But this time I already got the city to support us, and city office supported this construction.
10)Ryo
Ryo does not act violently any more. He has own place and friends. Gradually he regained his memory. He never even slightly loses his temper. When I mentioned how he acted violently, he laughed and said he was still a child at that time. He likes English and studies English Grammar by PC by himself. He writes short stories in English. He also likes karaoke and goes to karaoke shop alone to sing songs .He spends long hours singing songs with his companions.
These past 20 years have been very long. First I was involved in this work for Ryo. I had to do something for Ryo. But during the process, my origin to do this work changed to anger at the administration. I am still fighting against prejudice and negligence of handicapped people. I am fighting with the administration on behalf of handicapped people. My friends often wonder how I can act like this without crying.
Actually I never cried even when I was told by doctors that there was a 99.9% chance Ryo could not survive. I really never gave up his surviving. The sentence of 99.9% impossibility of surviving gave me the energy to make him survive. I did not accept this sentence seriously, I only thought he can survive, and I did everything what I could.
I believe my next dream will come true, too. That is the progress convincing the administration dealing with handicapped people to make them aware what being handicapped really is, and what they have to do for handicapped as administration without prejudice.
Above I have written my struggle for establishing Bakery Caffe Wind, Group Home Green Wind, and Regional life support Center NPO. I really want to know about the welfare in the world for cases like Ryo’s.; how administration is facing them in the world. What kind of organizations and institutions exist.
I would appreciate it if someone in the world who is involved in this field could send me some information. Also I want to let the people know my struggle as it is written above.
誰もがいつ障害者になるか誰もが考えてほしい事です。誰もが希望を持って生きていける社会作りに関心を持っていただきたく、いろんな国の人達の意見が聞きたいと英文にしました。
NPO法人 風 理事長 岸 俊子
Posted by かぜ at
11:54
│Comments(0)
2013年09月12日
【英文】 Sakuyahime Project Page1
Support for mental patients who are in the shade of public aid
Toshiko Kishi is one of the nominated members of the Sakuya Hime Project.
(A project to build a gender-equal human resource debate in Shizuoka .
The Sakuyahime project aims to empower Shizuoka women and develop female leaders for the next age. It was launched in 2010 by the Shizuoka Prefectural Government Office.) Toshiko is a mother who lives in Fujieda city in Shizuoka Prefecture, Japan, making a great effort to provide a place for mental patients who are in the shade of public aid.
Toshiko Kishi is the C.E.O of the N.P.O Group home and restaurant “Bakery Caffe Wind”. Written below is the process of how she started this project.
1).Tragedy
The tragedy when my second son Ryo was involved in an accident on the way back home from playing outside on his bicycle happened in September, 1992. When I was cooking dinner, my neighbor suddenly rushed into my home shouting “Ryo, Ryo! He was involved in an accident “.She said he was hit by a car. I dashed to the place where the accident happened, close to my house. He had been run over by a car coming the wrong way on the one-way road. Ryo had already lost consciousness, the right side of his head was crushed and a line of blood was running from his ear. He was not breathing. An ambulance took him to the hospital and an operation was done immediately, but the doctors told me that there was no hope of survival because not only his right brain, but left brain was the damaged, too. There is a 99.9 % chance he will not survive. There is no way to make him survive. I told the doctors “ If you say no hope of 99.9 %, there is a 0.1% hope, I bet on 0.1%. Open his head again now, in front of me. I will never regret even if he dies with that operation.” I begged the doctors. I did not want to give up 0.1 hope. Heisei Memorial Hospital is a well-known hospital for brain surgery. Doctors granted my request, and an operation was done again. I even thought if this operation turns out to be an experiment on the human body, I would accept it. After the operation the result was that his consciousness did not come back, but at least he did not die at that time. Doctors said “We can’t tell that he can live one day or two days, There is the possibility of his becoming a human vegetable.” At least I was satisfied that he could survive by the operation .I was given the hope he might be able to live one day longer. Actually he could live three days, I told the doctors. “He can live three days.” Doctors only answered ,“Yes, he can.” He lived four days ,five days and at last one week passed since the doctors had given up.
The person who caused the accident came and said, “How can I pray?” I only answered, “Pray for him that today’s situation lasts even one day longer”. I was not thinking he was cured, I just hoped to keep him living even one day longer.
In the ICU, I kept playing CD player, making him listen to music. After one week passed, an examination of the brain waves was done, and surprisingly his brain waves were rising slightly. This showed proof that his brain was not dead, but still in unconsciousness. Also he was not breathing by himself. Doctors gave me permission to do everything that I wanted to do.
His skull was severely damaged, only the center of the skull remaining. That means his brain was not covered by the skull. If something touched his brain, his life was endangered. I made a floss pillow and put it around his head also I put my two knees preventing anything from touching his headt, and kept playing CD, and cauterized moxibustion point . I was waching his face for 24 hours except going to the toiret.
I tried everything that I could do. I was surprised that doctors gave me permission to do everything. Nurses and other patients encouraged me. Ryo’s consciousness did not come back, his condition was still remaining the same. But the miraculous thing happened, I saw his fingers were moving. Doctors did not trust me and said “It can’t be happening.’ Since then doctors began to think that he might survive. His condition was improving rapidly. One day, he began to say something, one by one, ‘o’-“ka”-“a”-“san” connecting each sound that he said was, “take me to the hospital by your red car.”
At that time I had a red car. I had the confidence that he must have said “Mother, take me to the hospital by your red car.” He definitely said that. It was his first word after the accident. He must have remembered the time of the accident.
2). Unexpected After Effect of Miraculous Recovery
Soon after that, he opened his eyes, although the right eye was crushed and blind. He couldn’t stand up, let alone walk. Because most of his brain was damaged, it did not function. Miraculously, even though he had lost all his memory, he could recognize me saying “mother”.
Doctors gave me the fragments of his skull. I tried to put them together trying to remake his skull by using strong glue and cement. A new skull was made, but if something touched his head, he got the extreme pain. He expressed his pain as “my head is exploding.”
He left the hospital in December three months after the accident happened, and went to school from January (in Japan third term begins in January.) It was a miracle! When he was involved in the accident, his brain damage was too big, doctors completely gave up on saving his life. It might sound like he recovered rapidly, but not rapidly, little by little taking time. At the same time a more difficult time began. After effects of the brain damage caused many kinds of problems.
His frontal lobe, the front part of the brain necrosed, which made him lose emotional control. Above all, many places in his brain hurt. He had an epileptic fit. He went on the rampage. He continued to be hospitalized repeatedly.
I think when he got back his consciousness after three months passed, he was born again as a thirteen year old boy. Only three months made him a thirteen year old boy. There was an imbalance, which he had to adjust himself by battling with the after effects.
Doctors advised me that I might be thinking he is recovering in this pace, but his condition is not simple as I thought. Actually I didn’t have any doubt about his speedy recovery which occurred in this three months. Unfortunately he did not recover as I imagined. I took him to a lot of hospitals searching for ways and doctors to cure him.
One day in the car, on the way to the hospital he suddenly lost the emotional control and began to behave violently. I can’t tell how many times I was endangered by his behavior.
My son’s accident made me start my presents work. I was ignorant about welfare. Through my experience I got to know how families who have mental patients suffer from hardships.
3).Ryo’s case
There were no institutions to accept him. He has both social handicaps and mental handicaps. At the institutions for social handicap, his intellectual level is high, and he could not communicate with mental patients in the mental hospitals.
He went to the local elementally school, but he couldn’t keep pace with other children.
He grew up to the age of junior high school, but he could not go to school every day.
Teachers suggested he to go to school for handicapped children, but he was different from the handicapped children born by nature. He refused to go to the school for handicapped children. He went to local night high school. But he went to school just
One day. I looked for a school or institution to suit him and found one in Nagoya. Nagoya is very far from Fujieda city. He would have to live in the dormitory. He did not want to stay there, and escaped from school on the day he arrived. He did not know how to come back home. He had to ask people how to buy the train ticket.
The last choice for him was a mental hospital. He was hospitalized in a mental hospital, but patients are permitted to stay there three months at the longest. He stayed for three months and came back home and went on a rampage. Such conditions continued.
I was completely exhausted. Sometimes I wished for his death. When he had his accident, I did everything to help him survive. I only prayed for his survival, but I really wished for his death at that time. Never had I thought such a thing before.
Toshiko Kishi is one of the nominated members of the Sakuya Hime Project.
(A project to build a gender-equal human resource debate in Shizuoka .
The Sakuyahime project aims to empower Shizuoka women and develop female leaders for the next age. It was launched in 2010 by the Shizuoka Prefectural Government Office.) Toshiko is a mother who lives in Fujieda city in Shizuoka Prefecture, Japan, making a great effort to provide a place for mental patients who are in the shade of public aid.
Toshiko Kishi is the C.E.O of the N.P.O Group home and restaurant “Bakery Caffe Wind”. Written below is the process of how she started this project.
1).Tragedy
The tragedy when my second son Ryo was involved in an accident on the way back home from playing outside on his bicycle happened in September, 1992. When I was cooking dinner, my neighbor suddenly rushed into my home shouting “Ryo, Ryo! He was involved in an accident “.She said he was hit by a car. I dashed to the place where the accident happened, close to my house. He had been run over by a car coming the wrong way on the one-way road. Ryo had already lost consciousness, the right side of his head was crushed and a line of blood was running from his ear. He was not breathing. An ambulance took him to the hospital and an operation was done immediately, but the doctors told me that there was no hope of survival because not only his right brain, but left brain was the damaged, too. There is a 99.9 % chance he will not survive. There is no way to make him survive. I told the doctors “ If you say no hope of 99.9 %, there is a 0.1% hope, I bet on 0.1%. Open his head again now, in front of me. I will never regret even if he dies with that operation.” I begged the doctors. I did not want to give up 0.1 hope. Heisei Memorial Hospital is a well-known hospital for brain surgery. Doctors granted my request, and an operation was done again. I even thought if this operation turns out to be an experiment on the human body, I would accept it. After the operation the result was that his consciousness did not come back, but at least he did not die at that time. Doctors said “We can’t tell that he can live one day or two days, There is the possibility of his becoming a human vegetable.” At least I was satisfied that he could survive by the operation .I was given the hope he might be able to live one day longer. Actually he could live three days, I told the doctors. “He can live three days.” Doctors only answered ,“Yes, he can.” He lived four days ,five days and at last one week passed since the doctors had given up.
The person who caused the accident came and said, “How can I pray?” I only answered, “Pray for him that today’s situation lasts even one day longer”. I was not thinking he was cured, I just hoped to keep him living even one day longer.
In the ICU, I kept playing CD player, making him listen to music. After one week passed, an examination of the brain waves was done, and surprisingly his brain waves were rising slightly. This showed proof that his brain was not dead, but still in unconsciousness. Also he was not breathing by himself. Doctors gave me permission to do everything that I wanted to do.
His skull was severely damaged, only the center of the skull remaining. That means his brain was not covered by the skull. If something touched his brain, his life was endangered. I made a floss pillow and put it around his head also I put my two knees preventing anything from touching his headt, and kept playing CD, and cauterized moxibustion point . I was waching his face for 24 hours except going to the toiret.
I tried everything that I could do. I was surprised that doctors gave me permission to do everything. Nurses and other patients encouraged me. Ryo’s consciousness did not come back, his condition was still remaining the same. But the miraculous thing happened, I saw his fingers were moving. Doctors did not trust me and said “It can’t be happening.’ Since then doctors began to think that he might survive. His condition was improving rapidly. One day, he began to say something, one by one, ‘o’-“ka”-“a”-“san” connecting each sound that he said was, “take me to the hospital by your red car.”
At that time I had a red car. I had the confidence that he must have said “Mother, take me to the hospital by your red car.” He definitely said that. It was his first word after the accident. He must have remembered the time of the accident.
2). Unexpected After Effect of Miraculous Recovery
Soon after that, he opened his eyes, although the right eye was crushed and blind. He couldn’t stand up, let alone walk. Because most of his brain was damaged, it did not function. Miraculously, even though he had lost all his memory, he could recognize me saying “mother”.
Doctors gave me the fragments of his skull. I tried to put them together trying to remake his skull by using strong glue and cement. A new skull was made, but if something touched his head, he got the extreme pain. He expressed his pain as “my head is exploding.”
He left the hospital in December three months after the accident happened, and went to school from January (in Japan third term begins in January.) It was a miracle! When he was involved in the accident, his brain damage was too big, doctors completely gave up on saving his life. It might sound like he recovered rapidly, but not rapidly, little by little taking time. At the same time a more difficult time began. After effects of the brain damage caused many kinds of problems.
His frontal lobe, the front part of the brain necrosed, which made him lose emotional control. Above all, many places in his brain hurt. He had an epileptic fit. He went on the rampage. He continued to be hospitalized repeatedly.
I think when he got back his consciousness after three months passed, he was born again as a thirteen year old boy. Only three months made him a thirteen year old boy. There was an imbalance, which he had to adjust himself by battling with the after effects.
Doctors advised me that I might be thinking he is recovering in this pace, but his condition is not simple as I thought. Actually I didn’t have any doubt about his speedy recovery which occurred in this three months. Unfortunately he did not recover as I imagined. I took him to a lot of hospitals searching for ways and doctors to cure him.
One day in the car, on the way to the hospital he suddenly lost the emotional control and began to behave violently. I can’t tell how many times I was endangered by his behavior.
My son’s accident made me start my presents work. I was ignorant about welfare. Through my experience I got to know how families who have mental patients suffer from hardships.
3).Ryo’s case
There were no institutions to accept him. He has both social handicaps and mental handicaps. At the institutions for social handicap, his intellectual level is high, and he could not communicate with mental patients in the mental hospitals.
He went to the local elementally school, but he couldn’t keep pace with other children.
He grew up to the age of junior high school, but he could not go to school every day.
Teachers suggested he to go to school for handicapped children, but he was different from the handicapped children born by nature. He refused to go to the school for handicapped children. He went to local night high school. But he went to school just
One day. I looked for a school or institution to suit him and found one in Nagoya. Nagoya is very far from Fujieda city. He would have to live in the dormitory. He did not want to stay there, and escaped from school on the day he arrived. He did not know how to come back home. He had to ask people how to buy the train ticket.
The last choice for him was a mental hospital. He was hospitalized in a mental hospital, but patients are permitted to stay there three months at the longest. He stayed for three months and came back home and went on a rampage. Such conditions continued.
I was completely exhausted. Sometimes I wished for his death. When he had his accident, I did everything to help him survive. I only prayed for his survival, but I really wished for his death at that time. Never had I thought such a thing before.
Posted by かぜ at
11:49
│Comments(0)
2013年09月12日
さくや姫プロジェクト その2
10年目の限界と支え続けるために必要な支援 ただ「ベーカリーカフェ風」は、設立以来、公的な支援を一切もらわずに運営しています。この10年間、地元をはじめ、たくさんのお客さんが支え続けてくださったおかげで、何とかやってくることができました。お客さんたちの温かい心に対し、「障害者が作った」ということに寄りかかることなく、「本当にいい材料でいいものを作ろう」と頑張ってきたんです。
公的支援がなくても何とか経営はできます。しかし、それは私が睡眠を2時間まで削って、皆のお給料と運営費を確保してきたからなんですね。もうそろそろ限界です。今後は本当に公的支援が欲しい。
公的支援や就労継続支援事業(B型)指定にしてほしいというお願いは、これまでもしてきました。そのために市役所へ何度足を運んだかわかりません。私は本当に自分が捧げられるすべての体力と気力と財産を、障害のある人たちのために絞り出してきたんです。彼らが自立できるよう、もっと強力にサポートしたいですし、サービスも充実させたい。しかし個人でやっていくには、与えられた時間も経済力も限界があります。
あるとき、市役所の福祉課の担当者に「あなたはただのパン屋じゃないか」と言われたことがあります。何の補助ももらっていないから「ただのパン屋」というわけです。でもそれはおかしい。私は金儲けや自分の趣味で、ベーカリーカフェをやっているわけじゃありません。それは誰の目にも明らかだと思うんです。
「市内にあるB型施設は、どこもまだ定員的なゆとりがあるから、これ以上、B型施設はいらない」と言われたこともあります。でも、なぜ増やしてはいけないのか。その理由については釈然としません。市役所の職員だって、いろんな就職先のなかから市役所を選んだわけじゃないですか。どうして障害者には選ぶ自由がないのでしょうか。
行政で福祉に関わる人たちは、もっと「障害者目線」でものごとを捉えてほしいと思いますね。人間としての優しさを、仕事で発揮してほしい。障害があっても働く喜びや仲間がいる喜びは同じです。そもそも障害の有無は紙一重じゃないでしょうか。どっちが上か下かということではないはずです。犯罪を起こした「健常者」は社会的に見れば「障害」であるはずです。それでも、もし自分は健常者という人が「あなたたちは障害者だ」と言うのなら、どんな人も社会で幸せに生きるために、健常者としての役割を果たすべきでしょう。
仲間と居場所があったから実現した変化 2008年に作った「藤枝市地域支援センター風」は、ベーカリーカフェで仕事できない人たちが、軽作業や創作活動をして1日を過ごす憩いの場所です。もともとは私の自宅だったところをリフォームしました。30人ぐらいが登録していて、毎日10人ぐらいが利用しています。
今年1月には念願だった「グループホーム緑の風」をオープンしました。全部で8部屋の個室があって、寮母さんが部屋の掃除してくれたり、手作りのおいしい夕ご飯を作ってくれます。建物は私が自分のお金で建てましたが、すでに静岡県の認定がとれましたので、障害者のグループホームとして補助をいただいています。
グループホームができて、実はホッとしているんです。私は今年63歳になりますが、これで私にいつ何があっても、亮は生きていけるんじゃないかと思うんですね。かつてのように暴れて、警察や救急車を呼ぶことは、もうすっかりなくなりました。この1~2年は、ほんのちょっと怒るということさえありません。自分の居場所ができ、仲間もできて、少しずつ変わってきました。
記憶も取り戻しています。昔、暴れていたときのことを「あのときは子供だったから」と冗談みたいに言えるようになって、つくづく長い道のりだったなと思いますね。1年とか2年で何とかなることじゃありません。長いスタンスで捉える必要があります。
次の夢は障害と福祉をPRするチンドン屋 この18年間の活動は、全部息子のためとも言えますが、よくよく考えてみると、私自身、自分の居場所が欲しかったんじゃないかと思っています。暴力、暴力の毎日のなかで、「自分の生きた証」が欲しかった。暴力まみれの毎日で「このまま死ぬのはイヤだ」と思っていましたから。いろいろカッコいいこと言っていますが、それが本音ですね。
私の活動の源は怒りです。行政の人たちの保身や偏見、怠慢に対し、障害を持つ人たちに代わって今も闘っているし、そういう権力に負けたくない。自分の怒りにつぶされたくないから、行動しているんです。よく「俊子さんはそんなに大変な状況でよく泣かないわね」と友達に言われますが、悲しむと行動がとれなくなります。亮が99.9%助からないと言われたときも泣かなかったし、それがエネルギーになった。不可能と言われたことが、私のエネルギーになって、亮は今も生きています。
要するにいい加減なんでしょうね。深刻にならない。99.9%ダメだと言われても、「そうか」といい加減に受け止めれば、頑張ろうって気になれる。正直、私はあのとき「亮は死なない」と思っていたんです。
もう1つ、私がやり残している夢はチンドン屋です。うちのメンバー皆をチンドン屋にして、市役所の前を練り歩きたい。障害者に対する偏った見方を直してもらうためのプロモーションです。障害とはどういうものか、福祉とは何のためにあるのかをチンドン屋を通して考えてもらう。これまで思ったことは全部実現してきましたから、チンドン屋もきっと日の目をみると信じています。
岸 俊子
静岡県藤枝市生まれ 藤枝市在住
【 略 歴 】
1992 次男が交通事故に遭い、一命はとりとめるが重い後遺症を患うことに
1998 障害者が共同作業できる農園をスタート
2002 NPO法人「風」 設立
「ベーカリーカフェ風」をオープン
2008 「藤枝市地域活動支援センター風」開設
2011 「グループホーム緑の風」設立
公的支援がなくても何とか経営はできます。しかし、それは私が睡眠を2時間まで削って、皆のお給料と運営費を確保してきたからなんですね。もうそろそろ限界です。今後は本当に公的支援が欲しい。
公的支援や就労継続支援事業(B型)指定にしてほしいというお願いは、これまでもしてきました。そのために市役所へ何度足を運んだかわかりません。私は本当に自分が捧げられるすべての体力と気力と財産を、障害のある人たちのために絞り出してきたんです。彼らが自立できるよう、もっと強力にサポートしたいですし、サービスも充実させたい。しかし個人でやっていくには、与えられた時間も経済力も限界があります。
あるとき、市役所の福祉課の担当者に「あなたはただのパン屋じゃないか」と言われたことがあります。何の補助ももらっていないから「ただのパン屋」というわけです。でもそれはおかしい。私は金儲けや自分の趣味で、ベーカリーカフェをやっているわけじゃありません。それは誰の目にも明らかだと思うんです。
「市内にあるB型施設は、どこもまだ定員的なゆとりがあるから、これ以上、B型施設はいらない」と言われたこともあります。でも、なぜ増やしてはいけないのか。その理由については釈然としません。市役所の職員だって、いろんな就職先のなかから市役所を選んだわけじゃないですか。どうして障害者には選ぶ自由がないのでしょうか。
行政で福祉に関わる人たちは、もっと「障害者目線」でものごとを捉えてほしいと思いますね。人間としての優しさを、仕事で発揮してほしい。障害があっても働く喜びや仲間がいる喜びは同じです。そもそも障害の有無は紙一重じゃないでしょうか。どっちが上か下かということではないはずです。犯罪を起こした「健常者」は社会的に見れば「障害」であるはずです。それでも、もし自分は健常者という人が「あなたたちは障害者だ」と言うのなら、どんな人も社会で幸せに生きるために、健常者としての役割を果たすべきでしょう。
仲間と居場所があったから実現した変化 2008年に作った「藤枝市地域支援センター風」は、ベーカリーカフェで仕事できない人たちが、軽作業や創作活動をして1日を過ごす憩いの場所です。もともとは私の自宅だったところをリフォームしました。30人ぐらいが登録していて、毎日10人ぐらいが利用しています。
今年1月には念願だった「グループホーム緑の風」をオープンしました。全部で8部屋の個室があって、寮母さんが部屋の掃除してくれたり、手作りのおいしい夕ご飯を作ってくれます。建物は私が自分のお金で建てましたが、すでに静岡県の認定がとれましたので、障害者のグループホームとして補助をいただいています。
グループホームができて、実はホッとしているんです。私は今年63歳になりますが、これで私にいつ何があっても、亮は生きていけるんじゃないかと思うんですね。かつてのように暴れて、警察や救急車を呼ぶことは、もうすっかりなくなりました。この1~2年は、ほんのちょっと怒るということさえありません。自分の居場所ができ、仲間もできて、少しずつ変わってきました。
記憶も取り戻しています。昔、暴れていたときのことを「あのときは子供だったから」と冗談みたいに言えるようになって、つくづく長い道のりだったなと思いますね。1年とか2年で何とかなることじゃありません。長いスタンスで捉える必要があります。
次の夢は障害と福祉をPRするチンドン屋 この18年間の活動は、全部息子のためとも言えますが、よくよく考えてみると、私自身、自分の居場所が欲しかったんじゃないかと思っています。暴力、暴力の毎日のなかで、「自分の生きた証」が欲しかった。暴力まみれの毎日で「このまま死ぬのはイヤだ」と思っていましたから。いろいろカッコいいこと言っていますが、それが本音ですね。
私の活動の源は怒りです。行政の人たちの保身や偏見、怠慢に対し、障害を持つ人たちに代わって今も闘っているし、そういう権力に負けたくない。自分の怒りにつぶされたくないから、行動しているんです。よく「俊子さんはそんなに大変な状況でよく泣かないわね」と友達に言われますが、悲しむと行動がとれなくなります。亮が99.9%助からないと言われたときも泣かなかったし、それがエネルギーになった。不可能と言われたことが、私のエネルギーになって、亮は今も生きています。
要するにいい加減なんでしょうね。深刻にならない。99.9%ダメだと言われても、「そうか」といい加減に受け止めれば、頑張ろうって気になれる。正直、私はあのとき「亮は死なない」と思っていたんです。
もう1つ、私がやり残している夢はチンドン屋です。うちのメンバー皆をチンドン屋にして、市役所の前を練り歩きたい。障害者に対する偏った見方を直してもらうためのプロモーションです。障害とはどういうものか、福祉とは何のためにあるのかをチンドン屋を通して考えてもらう。これまで思ったことは全部実現してきましたから、チンドン屋もきっと日の目をみると信じています。
岸 俊子
静岡県藤枝市生まれ 藤枝市在住
【 略 歴 】
1992 次男が交通事故に遭い、一命はとりとめるが重い後遺症を患うことに
1998 障害者が共同作業できる農園をスタート
2002 NPO法人「風」 設立
「ベーカリーカフェ風」をオープン
2008 「藤枝市地域活動支援センター風」開設
2011 「グループホーム緑の風」設立
Posted by かぜ at
11:43
│Comments(1)
2013年09月12日
さくや姫プロジェクト その1
0.01%に望みを託して依頼した再手術 次男の亮が交通事故に遭ったのは1992年の9月。小学校6年生のときです。ちょうど2学期の始業式の日で、学校から帰ってきて、遊びに行った帰り道でした。夕飯の仕度をしていたら、近所の方が「亮くんが、亮くんが」って、真っ青な顔で飛んできて、近くの幹線道路で車にはねられたと言うんです。事故現場に飛んでいったら、既に意識はなくて、頭の右側半分が潰れていました。耳からひと筋、血が流れていて、もう息もしていません。救急車が来て、近くの平成記念病院に運んでもらいました。
すぐに手術をしたんですけれど、もう助からないと医者に言われました。「潰れたのは右側でしたが、左からも出血したので99.9%助かりません」。そう言われました。でも、「死ぬのを待つだけなら、もう1度、頭を開いて手術してください」と、先生にお願いしたんです。「この状態で手術するところなんかないですよ」と言われましたが、「その場で死んでもいい、手術に失敗してもいいから、もう1度頭を開いてください」と、無理を言ってお願いしたんです。99.9%ダメだというなら、残りの0.1%に賭けようと思ったんですね。
平成記念病院というのは個人病院ですが、脳外科では有名な病院です。2度目の手術には、内科や麻酔科からも先生を動員してくださった。人体実験でもいいと思ったんです。結局、意識は戻りませんでした。でも、少なくともそのときは死ななかった。「1日もつか、2日もつかはわかりません」と、先生には言われました。「もし、3日間生きたら、生き伸びるかもしれない。でも、植物状態になるかもしれません」とも。それはそれで良かったんです。私としては手術してもらったことで満足だったんですね。
3日間、生きました。「先生、3日間生きました」って言ったら、「そうだね」と言われただけでした。そのうち1週間生きたんです。事故の加害者の方が病院にいらして、「どう祈ったらいいですか?」と聞かれました。「今日の状態が明日も続くように――そう祈ってください」とお願いしたんです。「治ってほしい」というより「生きてほしい」という思いでした。
集中治療室では耳元で音楽を流し続けていた 何日かたって脳波の検査をしました。脳が死んでいると、脳波は真っ直ぐ平らです。ところが、ほんのちょっとだけ上がっていたんです。つまり、脳死ではなかったんですね。意識はないし、自分で呼吸もできないという状況がずっと続いていましたが、生きる可能性はあると思いました。
亮は集中治療室(ICU)にいました。今では考えられないことですが、先生が「どんなことをしてもいい」と許してくださった。
亮の頭蓋骨は事故でボロボロになってしまったので、真ん中の部分だけを残し、ほとんど全部取り除いた状態でした。脳が頭蓋骨に覆われていないので、仮に動いて何かにぶつかると、命が危ないと言われました。それで、大至急で真綿の布団を作りまして、亮の頭の周りをそれで囲って、さらにその外側から両足の内側で頭を挟み込むような格好で、私が枕元に座ったんです。24時間、トイレに行く以外は、ずっとそうして亮の顔を見ていました。
亮の耳元では、ずっと音楽をかけていました。モクモクと煙をたいてお灸をやったこともありましたね。そういうことを先生が許して下さったことは、今考えても驚きです。看護婦さんたちも応援してくださったし、他の患者さんたちも「亮君が生きたら、皆生きられるね」と励ましてくださった。
ずっと意識のない状態が続きました。ところが10日ぐらいたったとき、指がピクっと動いたんです。先生は「そんなことありえない」とおっしゃったのですが、確かに動いたんですね。最初は、なかなか先生が見ているところで動かなかったのですが、そのうち先生も指が動くのを見て、「もしかしたら生きるかもしれない」と――。
そこからは、トントン拍子でした。私は当時、赤い車に乗っていたんですが、あるとき「おー」「かー」「さー」「んー」と、うわ言みたいに本当に何かを話し始めたんです。意識は戻っていなかったのですが、1つひとつの言葉をつなぎ合わせていくと、「お母さんの赤い車で病院に僕を連れて行って」。そう言ったんです。事故現場で自分が倒れている姿を見ていたんでしょうかね。それが最初の言葉です。
奇跡の回復後に発症した予想以上の後遺症 そのうち目を開けました。右目は事故でつぶれてしまって、最初は見えませんでした。立つことも、歩くこともできませんでした。脳をやられてしまったので、そういう動作を身体が忘れてしまったんですね。最初は車椅子でリハビリです。記憶もなくしていましたが、私のことはすぐに「お母さん」とわかりました。不思議です。
事故でボロボロになった頭蓋骨の破片を、私は大事にとっておきました。使えそうな破片には穴を開け、パズルのように糸で縛ってつなぎ合わせて、埋まらない部分は速乾性のセメントを入れて、新しい頭蓋骨ができ上がりました。でも頭を触るだけで激痛が走るので、ずっとヘルメットをかぶっていました。その後、何年間も頭が爆発しそうに痛いと痛がって、髪の毛を洗うのもひと苦労でした。
12月に退院して、3学期からは学校に行きました。奇跡ですよね。事故直後は、99.9%助からないと言われたわけですから。こう話すと一気に回復したかのように聞こえるかもしれませんけれど、実際は薄紙をはがしていくように、毎日ほんの少しずつ回復していったんです。
しかし、大変だったのはその後の後遺症です。事故で頭が潰れたとき、前頭葉が壊死してしまって、感情をコントロールすることができなくなってしまったんですね。加えて脳の中が傷だらけになってしまった後遺症で、てんかんを発症しました。思春期だったということもあって暴れるんです。とりあえず始業式は行きましたけれど、学校には行けなくなり、あちこちの精神科で入退院を繰り返すことになりました。
亮は事故によって、生まれ直したようなものだと思うんですね。事故に遭ってから意識が戻るまでは、私のお腹に戻っていたようなものです。意識を取り戻したとき、「オギャー」と、もう一度生まれて、たった3カ月のうちに12歳になってしまった。そのひずみを、後遺症と闘いながら何年間もかけて調整してきたんだと思います。
平成記念病院の先生にも「お母さんは治ると思っていらっしゃるかもしれないけれど、そう簡単なものではありませんよ」と言われました。それがどういう意味なのか、具体的には言われなかったので、そのときはわからなかったんです。といいますか、そのときの私は、これだけ短期間で治ったんだから、同じペースでどんどん元気な亮に戻って行くことに何の疑いももっていませんでした。
でも、現実的にはそうならなかった。本当に県内あちこちのいろんな病院に行きました。今でも忘れられないのは、藤枝から浜松の病院に連れて行くとき。高速道路を走っていたんですが、私が運転している車の中で亮が暴れ出して、バックミラーを外すし、突然サイドブレーキ引くし……。私も命がけでした。
「この子が死んでくれたら」と思ったことも 私が今のような仕事をすることになったのは、すべて亮の交通事故がきっかけです。福祉というのは、それまで知らなかった世界ですね。障害をもつ人たちやその家族が、どんなに苦しんでいるかを初めて知りました。
亮の場合、受け入れ先がなかったんです。知的障害と精神障害、両方の障害があったので、知的障害の人たちだけがいる場所では知的レベルが高すぎるし、うつ病や統合失調症など、精神障害の人たちの中では、コミュニケーションがとれず困ってしまう。
事故の後も、普通の学校に通っていたのですが、勉強にはついていけませんでした。中学は行ったり行かなかったりで、先生が「養護学校へ行こう」と言ってくださったこともあります。でも、先天的な知的障害とは違いますから、本人のプライドが養護学校へ行くことを許さないわけです。
そんなふうでしたから高校も行くところがなくて、藤枝東高校の夜間に入れてもらったのですが、登校したのは1日だけ。先生も訪ねて来てくださったんですけど、結局行けないんです。その翌年、もう1度入学しましたが、やはり登校したのは1日だけでした。
名古屋に寮完備の素晴らしい施設を見つけて、連れていったこともあります。ところが夕飯のとき脱走して、線路を伝って駅を見つけ、そこから電車に乗って帰ってきてしまった。初日のうちにです。亮は脳外傷の後遺症で、方向がわかりません。ですから周囲の人たちに道を聞いて、切符の買い方も教えもらって、必死で戻ってきたんだと思います。
そうなると、精神病院以外に選択肢がないわけです。今も通院はしていますが、4年ぐらい前まで、何度も入退院を繰り返していました。ところが精神病院というのは、ずっと入院させてもらえないんです。3カ月が最長なので、すぐまた家に帰ってきます。帰って来てはまた暴れて……その繰り返しです。
そんな状況ですから、私は当然、外で働くことはできませんでした。正直、亮が暴れ出して手に負えなくなると、「この子が死んでくれたら」と思うこともありましたね。事故の後、あんなに「生きてほしい」と思っていたにもかかわらずです。亮は3人兄弟の真ん中なのですが、当時は亮だけでなく、主人や長男もよく暴れました。自分でも、どう乗り越えてきたのか、よくわかりません。毎日、ただ必死に生きてきただけです。
求む!国産小麦「ニシノカオリ」のタネ 病院や施設を転々とした結果、これはもう自分で亮の居場所を作るしかないと思うようになりました。それで1998年、近くに600坪の土地を借りて、農業を始めたんです。私、単純なんですね(笑)。経験がなくても土地があれば何かできるし、自然とのふれあいがいちばんいいんじゃないかと思ったのが、農業を選んだ理由です。
もう1つ、「社会に居場所がない人たち」の存在に気付いたということもあります。例えば、亮のように、精神障害と知的障害の両方を抱えているために、どちらの施設にも行けない「福祉の谷間」にいる人たち。亮の事故がきっかけになって、私の周りに、困った問題をかかえたお母さんが集まるようになったんです。
最初のメンバーは亮を入れて3人。キュウリやナスなど、無農薬で野菜を栽培していました。働く喜びを知ってほしかったので、まだ何も収穫がないうちから、時給150円出していました。私も収入はありませんから、自分の貯金からあげていたんです。
でも畑でも、亮は暴れ出すことがありました。農機具をもっているので怖いし、虫よけ用の網やシートを滅茶苦茶にしてしまうわけです。困ったなと思っていたとき、「そうだ麦を作ろう」とひらめいたんです。野菜よりも手がかからないと思ったんですね。ただの小麦じゃつまらないので、いろいろ調べているうちに「ニシノカオリ」という、パン作りに向いている小麦を見つけました。小麦は寒冷地で栽培されるものが多いのですが、「ニシノカオリ」は西日本の温暖地でも育つ新品種です。
そんなとき「国産小麦を楽しむ会」という会合が、都内のホテルで開かれることを知りました。2002年のことです。「ニシノカオリ」を作っている九州沖縄農業研究センターの方も参加されることがわかり、当日、1人で出かけて行ったんです。全国各地から研究者や業界関係者が集まった大きな会場で、マイクをつかんでこうお願いしたんです。「私は障害者と一緒に自分の畑で小麦を育て、皆でパンを作りたいと思っています。九州沖縄農業研究センターの方、どうぞニシノカオリのタネを譲ってください」。事前のお断りも約束もなしで、突然マイクをつかんでお願いしたんです。九州沖縄農業研究センターの方は快く「いいですよ」と、20キロのタネを送って下さった。
障害者が主役の「ベーカリーカフェ風」誕生 小麦の栽培は、口では説明できないくらい大変でした。何しろ私も含め、全員が素人です。その年は異常に梅雨が長くて、農薬を使っていないので、カビや赤ダニにやられそうになりました。刈る機械がなかったので、600坪に実ったムギを最終的には私1人で、雨のなか、鎌で刈っていったんです。刈り取ったムギを置く場所がなかったので、今度は近所じゅうの農家さんにお願いして、使っていない納屋やビニールハウスのスペースを貸してもらいました。素人の強さというか、知識がないからこそできたんでしょうね。
賠償金と自分の貯金とを合わせた資金で、2002年11月、「ベーカリーカフェ風」をオープンしました。実はずいぶん長い間、事故の賠償金というものがあること自体、気付かずにいたんです。2000年ある日、保険会社の人がやって来て「何か魂胆あるんですか?」と聞くんですね。最初は何のことかわかりませんでした。気がつけば、亮の事故から8年が過ぎていました。そのくらい毎日毎日、亮の病院探しに奔走して過ぎた8年間だったわけです。
「ベーカリーカフェ風」のオープンに先駆け、02年2月、NPO法人「風」を立ち上げました。ベーカリーカフェは、障害のある人たち、社会に居場所のない人たちが大勢集まって働ける場所をつくりたいというのが大きな狙いです。周囲に声を掛けたら、障害のある人たちが10人ぐらい、ボランティアも5~6人集まりました。自分たちで栽培した小麦でパンを製造して販売したり、イートインもできるカフェです。 当初は、障害者に対する偏見があったせいか、地元の人たちの間には惓厭ムードもありました。ベーカリーカフェがある助宗という地域は、古くから農家をやっているお宅が多く、住民のつながりも強いエリアです。1軒1軒ご挨拶に伺い、趣旨をお話しまして、少しずつ理解を得られるようになりました。今では、私に怒られた子が、泣きながら近所の家に飛び込んでいくと、お菓子をもらって帰ってきたり、なんていうことが結構あります。
すぐに手術をしたんですけれど、もう助からないと医者に言われました。「潰れたのは右側でしたが、左からも出血したので99.9%助かりません」。そう言われました。でも、「死ぬのを待つだけなら、もう1度、頭を開いて手術してください」と、先生にお願いしたんです。「この状態で手術するところなんかないですよ」と言われましたが、「その場で死んでもいい、手術に失敗してもいいから、もう1度頭を開いてください」と、無理を言ってお願いしたんです。99.9%ダメだというなら、残りの0.1%に賭けようと思ったんですね。
平成記念病院というのは個人病院ですが、脳外科では有名な病院です。2度目の手術には、内科や麻酔科からも先生を動員してくださった。人体実験でもいいと思ったんです。結局、意識は戻りませんでした。でも、少なくともそのときは死ななかった。「1日もつか、2日もつかはわかりません」と、先生には言われました。「もし、3日間生きたら、生き伸びるかもしれない。でも、植物状態になるかもしれません」とも。それはそれで良かったんです。私としては手術してもらったことで満足だったんですね。
3日間、生きました。「先生、3日間生きました」って言ったら、「そうだね」と言われただけでした。そのうち1週間生きたんです。事故の加害者の方が病院にいらして、「どう祈ったらいいですか?」と聞かれました。「今日の状態が明日も続くように――そう祈ってください」とお願いしたんです。「治ってほしい」というより「生きてほしい」という思いでした。
集中治療室では耳元で音楽を流し続けていた 何日かたって脳波の検査をしました。脳が死んでいると、脳波は真っ直ぐ平らです。ところが、ほんのちょっとだけ上がっていたんです。つまり、脳死ではなかったんですね。意識はないし、自分で呼吸もできないという状況がずっと続いていましたが、生きる可能性はあると思いました。
亮は集中治療室(ICU)にいました。今では考えられないことですが、先生が「どんなことをしてもいい」と許してくださった。
亮の頭蓋骨は事故でボロボロになってしまったので、真ん中の部分だけを残し、ほとんど全部取り除いた状態でした。脳が頭蓋骨に覆われていないので、仮に動いて何かにぶつかると、命が危ないと言われました。それで、大至急で真綿の布団を作りまして、亮の頭の周りをそれで囲って、さらにその外側から両足の内側で頭を挟み込むような格好で、私が枕元に座ったんです。24時間、トイレに行く以外は、ずっとそうして亮の顔を見ていました。
亮の耳元では、ずっと音楽をかけていました。モクモクと煙をたいてお灸をやったこともありましたね。そういうことを先生が許して下さったことは、今考えても驚きです。看護婦さんたちも応援してくださったし、他の患者さんたちも「亮君が生きたら、皆生きられるね」と励ましてくださった。
ずっと意識のない状態が続きました。ところが10日ぐらいたったとき、指がピクっと動いたんです。先生は「そんなことありえない」とおっしゃったのですが、確かに動いたんですね。最初は、なかなか先生が見ているところで動かなかったのですが、そのうち先生も指が動くのを見て、「もしかしたら生きるかもしれない」と――。
そこからは、トントン拍子でした。私は当時、赤い車に乗っていたんですが、あるとき「おー」「かー」「さー」「んー」と、うわ言みたいに本当に何かを話し始めたんです。意識は戻っていなかったのですが、1つひとつの言葉をつなぎ合わせていくと、「お母さんの赤い車で病院に僕を連れて行って」。そう言ったんです。事故現場で自分が倒れている姿を見ていたんでしょうかね。それが最初の言葉です。
奇跡の回復後に発症した予想以上の後遺症 そのうち目を開けました。右目は事故でつぶれてしまって、最初は見えませんでした。立つことも、歩くこともできませんでした。脳をやられてしまったので、そういう動作を身体が忘れてしまったんですね。最初は車椅子でリハビリです。記憶もなくしていましたが、私のことはすぐに「お母さん」とわかりました。不思議です。
事故でボロボロになった頭蓋骨の破片を、私は大事にとっておきました。使えそうな破片には穴を開け、パズルのように糸で縛ってつなぎ合わせて、埋まらない部分は速乾性のセメントを入れて、新しい頭蓋骨ができ上がりました。でも頭を触るだけで激痛が走るので、ずっとヘルメットをかぶっていました。その後、何年間も頭が爆発しそうに痛いと痛がって、髪の毛を洗うのもひと苦労でした。
12月に退院して、3学期からは学校に行きました。奇跡ですよね。事故直後は、99.9%助からないと言われたわけですから。こう話すと一気に回復したかのように聞こえるかもしれませんけれど、実際は薄紙をはがしていくように、毎日ほんの少しずつ回復していったんです。
しかし、大変だったのはその後の後遺症です。事故で頭が潰れたとき、前頭葉が壊死してしまって、感情をコントロールすることができなくなってしまったんですね。加えて脳の中が傷だらけになってしまった後遺症で、てんかんを発症しました。思春期だったということもあって暴れるんです。とりあえず始業式は行きましたけれど、学校には行けなくなり、あちこちの精神科で入退院を繰り返すことになりました。
亮は事故によって、生まれ直したようなものだと思うんですね。事故に遭ってから意識が戻るまでは、私のお腹に戻っていたようなものです。意識を取り戻したとき、「オギャー」と、もう一度生まれて、たった3カ月のうちに12歳になってしまった。そのひずみを、後遺症と闘いながら何年間もかけて調整してきたんだと思います。
平成記念病院の先生にも「お母さんは治ると思っていらっしゃるかもしれないけれど、そう簡単なものではありませんよ」と言われました。それがどういう意味なのか、具体的には言われなかったので、そのときはわからなかったんです。といいますか、そのときの私は、これだけ短期間で治ったんだから、同じペースでどんどん元気な亮に戻って行くことに何の疑いももっていませんでした。
でも、現実的にはそうならなかった。本当に県内あちこちのいろんな病院に行きました。今でも忘れられないのは、藤枝から浜松の病院に連れて行くとき。高速道路を走っていたんですが、私が運転している車の中で亮が暴れ出して、バックミラーを外すし、突然サイドブレーキ引くし……。私も命がけでした。
「この子が死んでくれたら」と思ったことも 私が今のような仕事をすることになったのは、すべて亮の交通事故がきっかけです。福祉というのは、それまで知らなかった世界ですね。障害をもつ人たちやその家族が、どんなに苦しんでいるかを初めて知りました。
亮の場合、受け入れ先がなかったんです。知的障害と精神障害、両方の障害があったので、知的障害の人たちだけがいる場所では知的レベルが高すぎるし、うつ病や統合失調症など、精神障害の人たちの中では、コミュニケーションがとれず困ってしまう。
事故の後も、普通の学校に通っていたのですが、勉強にはついていけませんでした。中学は行ったり行かなかったりで、先生が「養護学校へ行こう」と言ってくださったこともあります。でも、先天的な知的障害とは違いますから、本人のプライドが養護学校へ行くことを許さないわけです。
そんなふうでしたから高校も行くところがなくて、藤枝東高校の夜間に入れてもらったのですが、登校したのは1日だけ。先生も訪ねて来てくださったんですけど、結局行けないんです。その翌年、もう1度入学しましたが、やはり登校したのは1日だけでした。
名古屋に寮完備の素晴らしい施設を見つけて、連れていったこともあります。ところが夕飯のとき脱走して、線路を伝って駅を見つけ、そこから電車に乗って帰ってきてしまった。初日のうちにです。亮は脳外傷の後遺症で、方向がわかりません。ですから周囲の人たちに道を聞いて、切符の買い方も教えもらって、必死で戻ってきたんだと思います。
そうなると、精神病院以外に選択肢がないわけです。今も通院はしていますが、4年ぐらい前まで、何度も入退院を繰り返していました。ところが精神病院というのは、ずっと入院させてもらえないんです。3カ月が最長なので、すぐまた家に帰ってきます。帰って来てはまた暴れて……その繰り返しです。
そんな状況ですから、私は当然、外で働くことはできませんでした。正直、亮が暴れ出して手に負えなくなると、「この子が死んでくれたら」と思うこともありましたね。事故の後、あんなに「生きてほしい」と思っていたにもかかわらずです。亮は3人兄弟の真ん中なのですが、当時は亮だけでなく、主人や長男もよく暴れました。自分でも、どう乗り越えてきたのか、よくわかりません。毎日、ただ必死に生きてきただけです。
求む!国産小麦「ニシノカオリ」のタネ 病院や施設を転々とした結果、これはもう自分で亮の居場所を作るしかないと思うようになりました。それで1998年、近くに600坪の土地を借りて、農業を始めたんです。私、単純なんですね(笑)。経験がなくても土地があれば何かできるし、自然とのふれあいがいちばんいいんじゃないかと思ったのが、農業を選んだ理由です。
もう1つ、「社会に居場所がない人たち」の存在に気付いたということもあります。例えば、亮のように、精神障害と知的障害の両方を抱えているために、どちらの施設にも行けない「福祉の谷間」にいる人たち。亮の事故がきっかけになって、私の周りに、困った問題をかかえたお母さんが集まるようになったんです。
最初のメンバーは亮を入れて3人。キュウリやナスなど、無農薬で野菜を栽培していました。働く喜びを知ってほしかったので、まだ何も収穫がないうちから、時給150円出していました。私も収入はありませんから、自分の貯金からあげていたんです。
でも畑でも、亮は暴れ出すことがありました。農機具をもっているので怖いし、虫よけ用の網やシートを滅茶苦茶にしてしまうわけです。困ったなと思っていたとき、「そうだ麦を作ろう」とひらめいたんです。野菜よりも手がかからないと思ったんですね。ただの小麦じゃつまらないので、いろいろ調べているうちに「ニシノカオリ」という、パン作りに向いている小麦を見つけました。小麦は寒冷地で栽培されるものが多いのですが、「ニシノカオリ」は西日本の温暖地でも育つ新品種です。
そんなとき「国産小麦を楽しむ会」という会合が、都内のホテルで開かれることを知りました。2002年のことです。「ニシノカオリ」を作っている九州沖縄農業研究センターの方も参加されることがわかり、当日、1人で出かけて行ったんです。全国各地から研究者や業界関係者が集まった大きな会場で、マイクをつかんでこうお願いしたんです。「私は障害者と一緒に自分の畑で小麦を育て、皆でパンを作りたいと思っています。九州沖縄農業研究センターの方、どうぞニシノカオリのタネを譲ってください」。事前のお断りも約束もなしで、突然マイクをつかんでお願いしたんです。九州沖縄農業研究センターの方は快く「いいですよ」と、20キロのタネを送って下さった。
障害者が主役の「ベーカリーカフェ風」誕生 小麦の栽培は、口では説明できないくらい大変でした。何しろ私も含め、全員が素人です。その年は異常に梅雨が長くて、農薬を使っていないので、カビや赤ダニにやられそうになりました。刈る機械がなかったので、600坪に実ったムギを最終的には私1人で、雨のなか、鎌で刈っていったんです。刈り取ったムギを置く場所がなかったので、今度は近所じゅうの農家さんにお願いして、使っていない納屋やビニールハウスのスペースを貸してもらいました。素人の強さというか、知識がないからこそできたんでしょうね。
賠償金と自分の貯金とを合わせた資金で、2002年11月、「ベーカリーカフェ風」をオープンしました。実はずいぶん長い間、事故の賠償金というものがあること自体、気付かずにいたんです。2000年ある日、保険会社の人がやって来て「何か魂胆あるんですか?」と聞くんですね。最初は何のことかわかりませんでした。気がつけば、亮の事故から8年が過ぎていました。そのくらい毎日毎日、亮の病院探しに奔走して過ぎた8年間だったわけです。
「ベーカリーカフェ風」のオープンに先駆け、02年2月、NPO法人「風」を立ち上げました。ベーカリーカフェは、障害のある人たち、社会に居場所のない人たちが大勢集まって働ける場所をつくりたいというのが大きな狙いです。周囲に声を掛けたら、障害のある人たちが10人ぐらい、ボランティアも5~6人集まりました。自分たちで栽培した小麦でパンを製造して販売したり、イートインもできるカフェです。 当初は、障害者に対する偏見があったせいか、地元の人たちの間には惓厭ムードもありました。ベーカリーカフェがある助宗という地域は、古くから農家をやっているお宅が多く、住民のつながりも強いエリアです。1軒1軒ご挨拶に伺い、趣旨をお話しまして、少しずつ理解を得られるようになりました。今では、私に怒られた子が、泣きながら近所の家に飛び込んでいくと、お菓子をもらって帰ってきたり、なんていうことが結構あります。
Posted by かぜ at
11:38
│Comments(0)